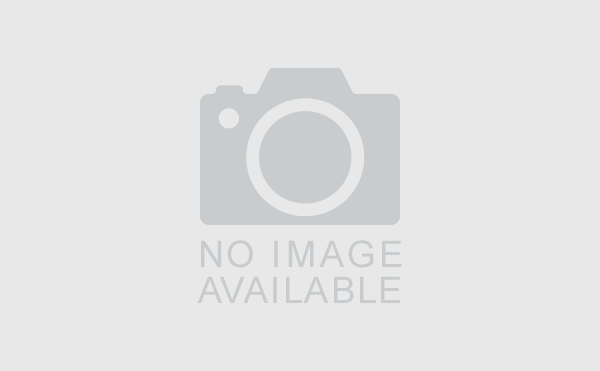変わる中小零細企業の新卒採用環境
以前に比べると、中小零細企業の新卒学生の採用を試みる中小零細企業がやや増える傾向にあります。今回は新卒採用の中でも、四大文系学生の場合を中心に考えてみましょう。
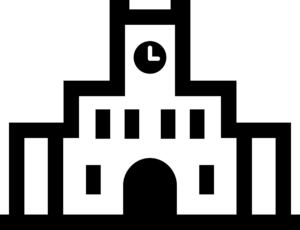 新卒採用には中途採用とは異なる特徴が二つあります。一つは採用のリスクが低いことです。中途採用は採用したい人材イメージを絞っても、ぴったりの人材が採りにくく、その結果、採用コストが膨大になってしまいがちです。それに対して新卒採用は新卒学生が登場する「源」が学校である上に、タイミングは卒業前の一定期間なので、中途採用に比べると採用活動が「読みやすい」ことになります。
新卒採用には中途採用とは異なる特徴が二つあります。一つは採用のリスクが低いことです。中途採用は採用したい人材イメージを絞っても、ぴったりの人材が採りにくく、その結果、採用コストが膨大になってしまいがちです。それに対して新卒採用は新卒学生が登場する「源」が学校である上に、タイミングは卒業前の一定期間なので、中途採用に比べると採用活動が「読みやすい」ことになります。
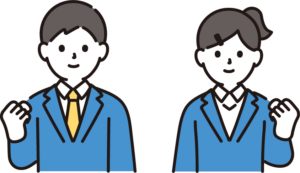 もう一つの特徴は、中途採用者の評価はその人材の「過去」の経験を軸に行なうものであるのに対して、新卒者は会社側が「未来」においてどう育てるかを意識して行なうものであることです。長期計画が立てにくく、柔軟な経営が求められる中小零細企業では、過去の経験から「活躍の仕方」が決まっている中途採用者は原理的には不都合が出やすいと考えることもできます。
もう一つの特徴は、中途採用者の評価はその人材の「過去」の経験を軸に行なうものであるのに対して、新卒者は会社側が「未来」においてどう育てるかを意識して行なうものであることです。長期計画が立てにくく、柔軟な経営が求められる中小零細企業では、過去の経験から「活躍の仕方」が決まっている中途採用者は原理的には不都合が出やすいと考えることもできます。
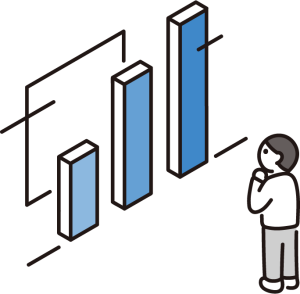 こうした中小零細企業の新卒採用ですが、特に新型コロナ禍以降、大分、変化して来ました。その主要因は、売り手市場になったことです。企業も優れた学生を確保しようと、早い段階から採用活動を始めるようになりました。インターンシップなども実質的な採用活動と見なすと、今では「就活」は2年生の終わりぐらいから始まっています。
こうした中小零細企業の新卒採用ですが、特に新型コロナ禍以降、大分、変化して来ました。その主要因は、売り手市場になったことです。企業も優れた学生を確保しようと、早い段階から採用活動を始めるようになりました。インターンシップなども実質的な採用活動と見なすと、今では「就活」は2年生の終わりぐらいから始まっています。
 勿論、4年生の公務員試験受験の失敗後に民間企業への就活に向かう学生などもいますので、「就活」と呼ばれる活動の期間が全体で見ると2年生終盤から4年生終盤までまるまる2年以上続くことになってしまったのです。その期間の中で、学校学部の偏差値が高ければ高いほど、学生が優秀であればあるほど、原理的には早い時期に決まっていきます。一方で、採用作業専従者を置くことが難しい中小零細企業が早い段階に内定を出しても、その後2年間も内定者を囲い込んでおくのは非常に困難ですから、大手企業に伍した早いタイミングの採用もできません。
勿論、4年生の公務員試験受験の失敗後に民間企業への就活に向かう学生などもいますので、「就活」と呼ばれる活動の期間が全体で見ると2年生終盤から4年生終盤までまるまる2年以上続くことになってしまったのです。その期間の中で、学校学部の偏差値が高ければ高いほど、学生が優秀であればあるほど、原理的には早い時期に決まっていきます。一方で、採用作業専従者を置くことが難しい中小零細企業が早い段階に内定を出しても、その後2年間も内定者を囲い込んでおくのは非常に困難ですから、大手企業に伍した早いタイミングの採用もできません。
 こうして「採用タイミングが絞り込める」という新卒採用の特徴が一般論では崩れて来ています。中小零細企業は自社が雇いたい学生イメージを的確に描いて、その対象学校や採用タイミングを個々に絞り込んで採用に当たる必要性が以前に比べて大きく高まってしまったのです。
こうして「採用タイミングが絞り込める」という新卒採用の特徴が一般論では崩れて来ています。中小零細企業は自社が雇いたい学生イメージを的確に描いて、その対象学校や採用タイミングを個々に絞り込んで採用に当たる必要性が以前に比べて大きく高まってしまったのです。