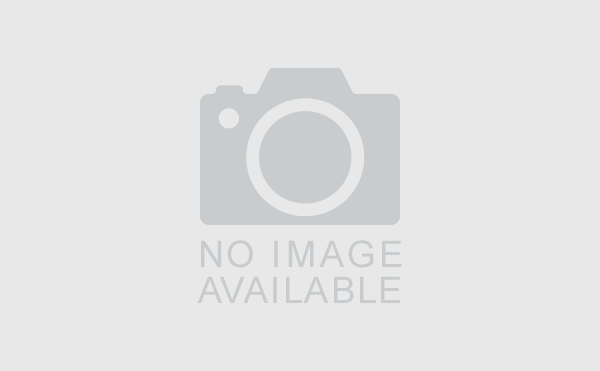本気の離職抑制の下準備は何が必要?
 以前離職抑制の記事を発表しておりますが、大企業に入社する人材より、中小零細企業に入社する人材の方が若干見劣りする、というお話をいたしました。だからこそ、大手企業で有効と言われる離職抑制策の適用には無理があるケースが多いことが分かります。中小零細企業での離職抑制の最強の手法は、実は育成なのです。ならば直ぐにも育成を始めたい所ですが、その前にやっておかねばならないことがいくつかあります。
以前離職抑制の記事を発表しておりますが、大企業に入社する人材より、中小零細企業に入社する人材の方が若干見劣りする、というお話をいたしました。だからこそ、大手企業で有効と言われる離職抑制策の適用には無理があるケースが多いことが分かります。中小零細企業での離職抑制の最強の手法は、実は育成なのです。ならば直ぐにも育成を始めたい所ですが、その前にやっておかねばならないことがいくつかあります。
■最低限のコンプライアンス体制
 後述するような育成を従業員に対して行なえば、従業員は戦力化する一方で、現実的な社会常識をも身につけ、自社やそこでの自分の立場を俯瞰できるようになります。そうなった際に、自社の経営があからさまな脱法行為や違法行為を含んでいるのでは、それらの重大性が分かるようになるが故に、従業員はむしろ離職の道を選ぶでしょう。それどころか内部告発なども発生するかもしれません。ですので、業界慣習などでたとえ同業他社も同様のことをしていたとしても、最低限のコンプライアンス体制は確立しておく必要があります。
後述するような育成を従業員に対して行なえば、従業員は戦力化する一方で、現実的な社会常識をも身につけ、自社やそこでの自分の立場を俯瞰できるようになります。そうなった際に、自社の経営があからさまな脱法行為や違法行為を含んでいるのでは、それらの重大性が分かるようになるが故に、従業員はむしろ離職の道を選ぶでしょう。それどころか内部告発なども発生するかもしれません。ですので、業界慣習などでたとえ同業他社も同様のことをしていたとしても、最低限のコンプライアンス体制は確立しておく必要があります。
■就業規則・給与制度の整備
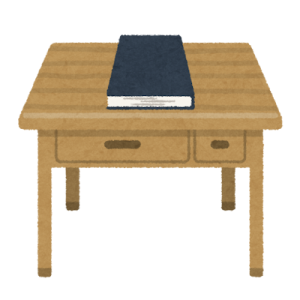 同様に、就業規則や給与制度も整備しておく必要があるでしょう。給与も社長の主観的な判断で決められているような中小零細企業もあるかと思います。それらを何か見栄えの良い制度に置換する必要はありません。今までやっていることに特に違法性がないなら、それをそのまま明文化し、説明を求められたら、説明ができるような体制にするだけで最低限はクリアできるでしょう。「オーナー経営者の好き嫌い人事」は、中堅企業サイズでもそれなりに罷り通っています。好き嫌いだとしても、一つの物差しで一貫性を以て公平に評価・処遇していることが重要なのです。
同様に、就業規則や給与制度も整備しておく必要があるでしょう。給与も社長の主観的な判断で決められているような中小零細企業もあるかと思います。それらを何か見栄えの良い制度に置換する必要はありません。今までやっていることに特に違法性がないなら、それをそのまま明文化し、説明を求められたら、説明ができるような体制にするだけで最低限はクリアできるでしょう。「オーナー経営者の好き嫌い人事」は、中堅企業サイズでもそれなりに罷り通っています。好き嫌いだとしても、一つの物差しで一貫性を以て公平に評価・処遇していることが重要なのです。
■育成体制の確立
後述するような育成体制を今後徹底して従業員に対して行なっていくにあたり、どのような育成をどのように抜けや漏れがないように行なっていくかを精緻に計画して、確実に実行できるようにしましょう。
 育成の計画をするには、採用するのが新卒者であろうと転職者であろうと、ターゲットとなるモデルを決め、どの程度の知識や常識レベルの人間が入ってくるのかを想定する必要があります。喩えて言うなら小学生が入ってくるのと中学生が入ってくるのではカリキュラムが変わって当然です。どれぐらいの人材を自社は雇おうとしているかによって育成の内容は全く様変わりするのです。
育成の計画をするには、採用するのが新卒者であろうと転職者であろうと、ターゲットとなるモデルを決め、どの程度の知識や常識レベルの人間が入ってくるのかを想定する必要があります。喩えて言うなら小学生が入ってくるのと中学生が入ってくるのではカリキュラムが変わって当然です。どれぐらいの人材を自社は雇おうとしているかによって育成の内容は全く様変わりするのです。
育成を日常業務の一環として位置付けて、やると決めたことは必ずやることも非常に重要です。繁忙期になると止めてしまったり、日常業務が主であって育成作業は「空き時間があったらやる作業」のように位置付けたりしないことです。繁忙期でも給与の支払もすれば、請求書の発行もします。同様に育成の業務もすべきです。
■風土変革
 前項で育成体制を確立しても、オーナー経営者が「笛吹けど踊らず」ではお話になりません。育成によって「分かる従業員」・「デキる従業員」を創り上げることが離職抑制には最善策で、離職抑制を行なわなければ自社は存亡の危機に立たされるという認識を、最低でも育成の最前線に立つ幹部・管理職クラスまでは徹底させましょう。ついでにこれらの人々には、言い訳をせず自責の感覚を持つようにこの機会に改めてもらいましょう。
前項で育成体制を確立しても、オーナー経営者が「笛吹けど踊らず」ではお話になりません。育成によって「分かる従業員」・「デキる従業員」を創り上げることが離職抑制には最善策で、離職抑制を行なわなければ自社は存亡の危機に立たされるという認識を、最低でも育成の最前線に立つ幹部・管理職クラスまでは徹底させましょう。ついでにこれらの人々には、言い訳をせず自責の感覚を持つようにこの機会に改めてもらいましょう。
前項で述べたように、取り分け、育成を日常業務として認識させるには、かなりの徹底が必要です。オーナー経営者は、その点について決して妥協しない姿勢が必要になります。